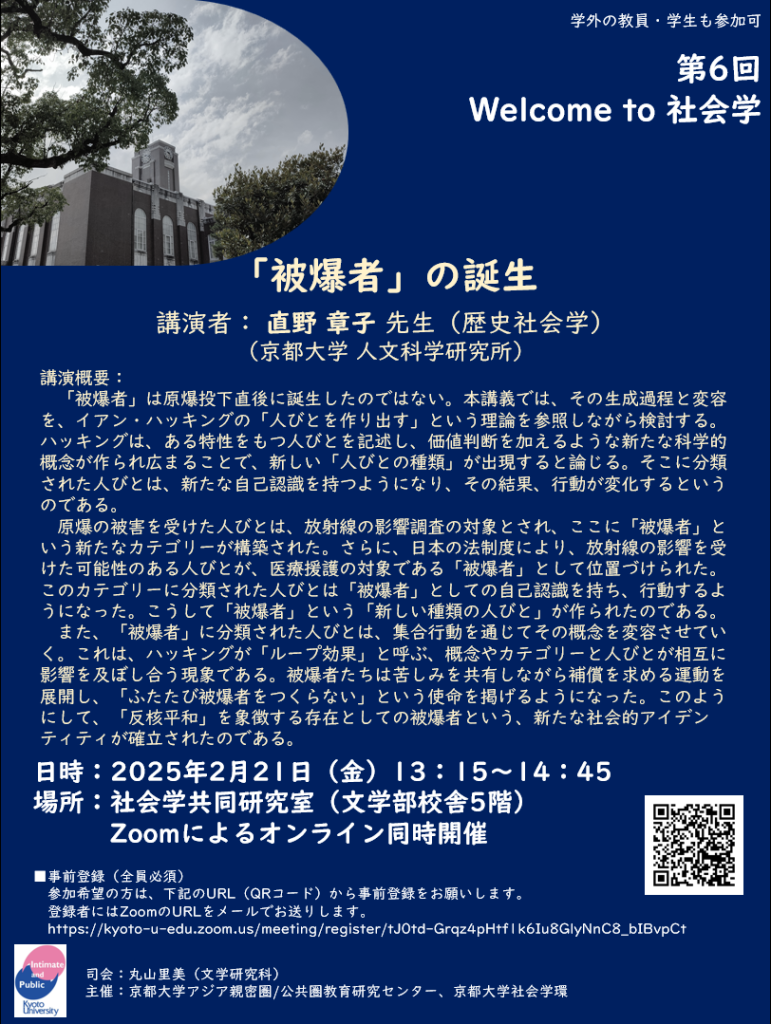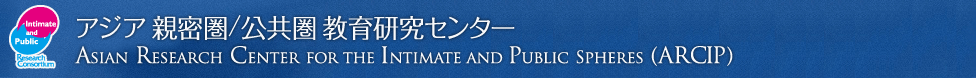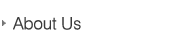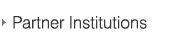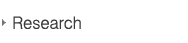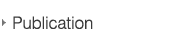ð¤˜Õ§ÍÊÏÍÙÎÐÏÐ₤ÐÓʃð¥ÍÙÎÍÕÐÛÌÍÀдÐÐÛÌͯÍÙÎÓÐÐÐЃÐЃЈÍÙÎÕ´Ð£Ó ÓˋÑÓÏÓÙШӿʹÐÐÎÐЃÐÐ
ÐÐÐÏÐÐÐÐÐÛÌÍÀУÍÙÎÓÐÛÐÌ´ˆÐÛÐÊЈÐÐÐÿ¥Óʃð¥ÍÙÎÓ¯ÿ¥ÐÌÇ£ÌÏÍÐÐÐдÐÐÐÐÐÎÐ
ð¤˜Õ§ÍÊÏÍÙÎÐÂСÐÂÒΈÍ₤Í/Í
˜Í
ÝÍÌÒýÓ ÓˋÑУаТХÐÏÐ₤ÐÐWelcome to Óʃð¥ÍÙÎÐдÐÐÓ ÓˋÑð¥ÿ¥ÐˆÐ˜Ð¥Ò˜Ì¥ð¥ÿ¥ÐÕ͘ÐÐÎÐÐЃÐÐ
Ì₤ÍÐÍÙÎÍ
ÐÛÓʃð¥ÍÙÎÍÕÐÛÌÍÀ1ÍШҘ̥ÐÐÎÐÐÐ ÐÐÐÐÛ̓ÐÒÇÒÀÐÛÌÍÀУÍÙÎÓÐð¤ÊÐÐÎÒˆÓÝÕÕЈҰˆÓÍ¢ÓÙÐÒÀÐЃÐÐ
ÿ¥ZoomШÐÐЈаÐˋÐÊаÍÌÕ͘ÐÍÙÎÍÊÐÛÌÍÀУÍÙÎÓÐÍÍ Í₤ÿ¥
ÐÐÛÐаÐÛÓ˜˜6ÍÐ₤ÐÌÙÇÍýÓʃð¥ÍÙÎÐÐͯÕÐÛÓÇÕÓ¨ ÍÙÍ
Óÿ¥ð¤¤ÌÓÏÍÙÎÓ ÓˋÑÌÿ¥Ð¨ÐҘ̥ÐÐÐ ÐЃÐÐ
ÿ¥Òˋ°ÓǯÐÒ´Ò¥ÐÐÐпТХPDFÐÌñ£ð£ÐÐÎÐÐЃÐÐÿ¥
ÐÐýÐÍÍ ÐÐ ÐÐÿ¥
ã ÐWelcome to Óʃð¥ÍÙÎÐÓ˜˜6Íÿ¥ÐˆÐ°ÐˋÐÊаÍÌÕ͘ÿ¥
ÌËÌÿ¥2025Í¿Ç2Ì21ÌËÿ¥Õÿ¥13:15ÿ§14:45
Í ÇÌÿ¥Óʃð¥ÍÙÎÍ
ÝÍÓ ÓˋÑÍÛÊÿ¥ÌÍÙÎÕ´Ì ÀÒ5Õÿ¥
Ҙ̥Ò
ÿ¥ÓÇÕÓ¨ ÍÙÍ
Óÿ¥ð¤¤ÌÓÏÍÙÎÓ ÓˋÑÌÿ¥
ÐÐ¥Ðÿ¥ÐÒ¨ÓÒ
ÐÐÛÒˆÓ
ÌÎÒÎÿ¥
ÐÒ¨ÓÒ
ÐÐ₤ÍÓÌð¡ÓÇ̓Ш҈ÓÐÐÐÛÐÏÐ₤ЈÐÐ̘ҘӃˋÐÏÐ₤ÐÐÐÛÓÌÕӴдÍÊÍÛ¿ÐÐÐÊÐÂаУÐÐÐÙаЯÐÛÐð¤¤Ð°Ð´Ðð§ÐͤÐÐдÐÐÓÒ¨ÐÍÓ
ÏÐЈÐÐÌÊÒ´ÐÐÐÐÐÐÙаЯÐ₤ÐÐÐÓ¿ÌÏÐÐÐÊð¤¤Ð°Ð´ÐÒ´Ò¢¯ÐÐðƒÀÍÊÍÊÌÙÐÍ ÐÐÐÐЈ̯ÐЈÓÏÍÙÎÓÌÎÍ¢çÐð§ÐÐͤЃÐÐдÐÏÐ̯ÐÐÐð¤¤Ð°Ð´ÐÛÓ´ÛÕÀÐÐͤӃÐÐдҨÐÐÐÐÐШÍÕÀÐÐÐð¤¤Ð°Ð´Ð₤Ð̯ÐЈ҈ÍñÝÒˆÒÙÐÌÐÊÐÐШЈÐÐÐÐÛÓçÌÐÒÀÍÐÍÊÍÐÐдÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐÍÓÐÛÒ¨ÍÛ°ÐÍÐÐð¤¤Ð°Ð´Ð₤Ð̃ͯÓñÐÛͧÝÕ¢Òˆ¢Ì£ÐÛÍ₤ƒÒÝÀдÐÐÐÐÐШÐÒ¨ÓÒ
ÐдÐÐ̯ÐЈШÐÐÇЈХÐÌÏÓ₤ÐÐÐÐÐÐШÐÌË̘ÐÛÌ°ÍÑͤÎШÐÐÐ̃ͯÓñÐÛͧÝÕ¢ÐÍÐÐÍ₤Ò§ÌÏÐÛÐÐð¤¤Ð°Ð´ÐÐÍ£ÓÌÇÒÙñÐÛÍ₤ƒÒÝÀÐÏÐÐÐÒ¨ÓÒ
ÐдÐÐÎð§Ó§ÛÐËÐÐÐÐÐÐÐÛШÐÐÇЈХШÍÕÀÐÐÐð¤¤Ð°Ð´Ð₤ÐÒ¨ÓÒ
ÐдÐÐÎÐÛÒˆÍñÝÒˆÒÙÐÌÐÀÐÒÀÍÐÐÐÐШЈÐÈÐÐÐÐÐÐÎÐÒ¨ÓÒ
ÐдÐÐÐ̯ÐÐÓ´ÛÕÀÐÛð¤¤Ð°Ð´ÐÐð§ÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ÐЃÐÐÐÒ¨ÓÒ
ÐШÍÕÀÐÐÐð¤¤Ð°Ð´Ð₤ÐÕÍÒÀÍÐÕÐÐÎÐÐÛÌÎÍ¢çÐÍÊÍÛ¿ÐÐÐÎÐÐÐÐÐÐ₤ÐÐÐÐÙаЯÐÐШХÐÍ¿ÌÐдͥÐÑÐÌÎÍ¢çÐШÐÐÇЈХдð¤¤Ð°Ð´ÐÓ¡ð¤Ð¨Í§ÝÕ¢ÐÍÐ¥ÐÍÐÓƒÒÝÀÐÏÐÐÐÒ¨ÓÒ
ÐÐÀÐ₤ÒÎÐТÐÍ
ÝÌÐЈÐÐÒÈÍÐÌÝÐÐÕÍÐÍÝÕÐÐÐÐçÐÐаÒ¨ÓÒ
ÐÐÊÐÐЈÐÐдÐÐð§¢Í§ÐÌýÐÐÐÐШЈÐÈÐÐÐÐÛÐÐШÐÐÎÐÐÍÌ ¡Í¿°ÍÐÐÒÝÀ̓ÇÐÐÍÙʹдÐÐÎÐÛÒ¨ÓÒ
дÐÐÐ̯ÐЈÓʃð¥ÓÐÂÐÊÐаÐÐÈÐÐÈÐÓ¤ӨÐÐÐÐÛÐÏÐÐÐ
ã ð¤ÍÓ£Õýÿ¥Í
´ÍÀÍ¢
Õ ÿ¥
ÐÍÍ Í¡ÌÐÛÌ¿Ð₤Ðð¡Ò´ÐÛURLÐÐð¤ÍÓ£ÕýÐÐÕÀÐÐЃÐÐ
ÐÓ£ÕýÒ
ШÐ₤ZoomÐÛURLÐÐÀХШÐÏÐÕÐÐЃÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
Ðhttps://kyoto-u-edu.zoom.us/meeting/register/tJ0td-Grqz4pHtf1k6Iu8GlyNnC8_bIBvpCt